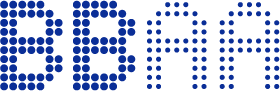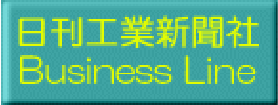協会活動報告と会員情報
【特別座談会】「BtoB 企業の企業博物館に必要な『もの』『こと』『考え方』」
2025-08-18
今回は「企業博物館に必要な『もの』『こと』『考え方』」というテーマで全国の企業博物館の開設を担当された制作会社の第一線のプランナーの方々にご参集いただきました。

- 司会
- 今回はご多忙の中お集まりいただき感謝しています。私は本誌に「企業博物館を観る」という連載を継続しているのですが、昨年、BtoB企業に所属し、運営責任をしておられる方々にご出席いただき座談会を開催したところ、非常に反響がありました。この種の座談会はなかなか実現する機会がなかったのですが、実施してみるとじつに意義のあるものとなりました。
そこで今回は、企業博物館を企画し開設までを担当するプランナーの方々に声をおかけしました。どんな話となるのか、非常に楽しみです。また今回も昨年同様、日本における企業博物館研究では第一人者の高柳先生にコーディネーターを務めていただきます。
まず皆さんの自己紹介からお願いします。
企業博物館をプランニング
- 小林
- 乃村工藝社の小林です。2007年から企業のコミュニケーションスペース全般を担当しています。そのため、BtoB・BtoCに関わらず、企画段階から最後のコンテンツ、グラフィック制作まで一貫して携わっています。最近の事例では、横浜のみなとみらいにある富士フイルムビジネスイノベーションの「Green Park FLOOP」を担当しました。ここは子供向けにサステナブルな地球の未来を探究する場でもありながら、ビジネス関連の来館者に複合機関連の技術を伝えるというBtoCとBtoBの両面を持つ場です。
- 島村
- トータルメディア開発研究所の島村です。わが社は行政や民間企業の博物館や文化施設に特化した展示の設計と制作を担当する会社です。私は入社以来「まほうびん記念館」など企業ミュージアムの整備をお手伝いすることが多いのですが、BtoBというケースで言うと大手の電子部品メーカーのミュージアムを手がけました。
- 渡邉
- 丹青社の渡邉です。もともとデザイナーで入社したのですが、プランニングを担当するようになり、企業ミュージアムや博物館といういわゆる広報施設に関わるようになり、工場見学施設なども担当しました。最近だと戸田建設グループの「TODA CREATIVE LAB “TODAtte?(トダッテ)”」に関わりました。この案件も含め、近年のプロジェクトは長期間の仕事が増えており、なんとなく時代の変化というものを感じています。
アテンド力がキーとなるBtoB施設
- 司会
- ありがとうございました。企業博物館は1980年代からできはじめ、2020年を越えてもまだ増え続けています。基本的には設置する企業のレピュテーション(優良な評価)の獲得が目的なので、幅広いステークホルダーにその企業のことを知ってもらいたいという意図があると考えます。まずお聞きしたいのは、皆さんが手がけられたケースで、BtoBとBtoCの違いを感じられたことはありますか。
- 小林
- BtoBの仕事をしていてBtoBとの違いを考えてみると、BtoBの企業は、知る人ぞ知る存在であることが多いと思います。BtoBもBtoCも設置している企業がどのように社会や世界に貢献しているのかを理解していただく事をゴールにしていると思うのですが、BtoBの場合、まず社名も知らないし、なにを作っているのかわからないが、説明を聞いたり展示を見たりすると、「こんな製品を作っているのか」「こんな高いシェアを持っているのか」と驚かれることがよくあります。だからこそ、アテンドの力が重要だと思います。
- 島村
- 共通することはあると思うのですが、BtoBでは来館者が、まず企業名も知らない。なにを作っているのかも認知できていない。でも実は世界のトップシェアを確保しているなどということがあります。BtoCでは「カップヌードルミュージアム」のように皆が知っている商品がどのように作られ、どのようなこだわりを持っているのかは理解できるのですが、BtoBの場合、一般には知られていない、技術力やソリューションをしっかり顕在化し来館者に伝える必要があります。そうなってくると作り方そのものもBtoCとは異なる発想やアプローチで取り組む必要があります。またBtoBの場合はインナー対応の要素が多いことと、取引先の来館者の比重が高いことなどターゲットの違いも大きいと思います。
- 渡邉
- お二人と重なることが多いのですが、BtoCとBtoBの施設を担当するとき、BtoCは割とブランドが立っており、そのことで、ブランドの世界観で押し切れることはありますが、BtoBは全方位的に攻めていく必要があると思います。また、BtoBの施設はアテンドが前提となるという特徴を感じます。体験ももちろん大事なのですが、エンパシー(共感)を得るやり方が必要だと感じています。
- 司会
- 前回の座談会で「ミツトヨ測定博物館」の方が、「近所の方が訪れて、こんな大きな会社が近くにあるけど、なにをしている企業か全然知らなかった。でも、見学して、こんなことをしていたんだと初めて理解した」ということを言っておられました。表から見る印象と、見学して感じることにすごいギャップがある。その意味でもBtoB企業の企業博物館はインパクトを感じます。
全部知って、さらに深く知る
- 高柳
- 先ほどの話にもありましたが、BtoB企業の場合、世間の認知度の低さがある中で、企画者が見せるものをピックアップしながらミュージアムをつくられていくと思うのですが、その作業プロセスで、これを見せた方が良いということを発見するためのコツや手法、あるいは意識しておられることについてお聞きしてもよろしいでしょうか。
- 小林
- 7月に日本ガイシの「NGKCollaborationSquare DIVERS」という施設が名古屋本社の敷地内にオープンします。日本ガイシはTVCMも放映しているので、セラミックスの企業という印象はなんとなく持たれているかもしれませんが、社名は聞いたことがあっても「なにを作っているのか」「その製品がどんなことに役立つのか」を理解するのが難しく、事業内容はあまり知られていません。つまり、企業の紹介というよりも、まずはその業界の話から伝える必要があるのです。「セラミックスとはなにか」というところから紐解いて、その中で自社の優位性を見出していく必要があります。
もう一点、10年ほど前に手がけた精密化学メーカーの施設があります。開設に至るまでの段階で、おそらく数十名の技術者の方々と面談を行いました。技術者の方々は、自身の研究領域に関しては熟知している一方で、他の分野のことは意外と知らなかったりする。そのため私たち外部の人間が、横断的に全体を把握する役割を担うことになったのです。もちろん社内で全体を把握されている方は存在すると思いますが、一度全体を把握した上で最大公約数的に整理し、その企業の強みを言語化していくことや分類する作業に取り掛かることで、全体の棚卸ができ、クライアント自身も気づいていなかったような強みを発見することもできるのです。
- 高柳
- 本来だとミュージアムをつくろうとしている企業側で出来ていると理想的なことを、皆さんのような企業ミュージアムのプランナーやディスプレイ業者の方々が、ミュージアムの企画をつくっていくプロセスで実現しているというのは興味深い話ですね。
- 島村
- 私の18番は「まほうびん記念館」や「フェザーミュージアム」のように、とにかく大量の実物資料を展示することです。実物資料だけでなく周辺物まですべてならべてしまうことからスタートする。それらを見ながら技術者の方々とのヒアリングを繰り返す。結果的にそのまま展示資料としても使用できるし、編集することも可能になるのです。
- 渡邉
- 見つけ方ですよね。結構泥臭い作業が非常に多いのですが、私自身はその企業に転職した気持で取り組んでいます。社史や企業の広報誌や社内報にもすべて目を通します。それを繰り返すうちに、企業としての中長期の視点が理解できる。自分がもしこの企業に所属していて、誰かに紹介する場合、それをどのように表現するのが大切なのかを考えるのです。そのためナラティブ(物語)化していっているような感じになります。
- 小林
- BtoB企業の方には理系出身の方が多い印象があります。私は文系なので、実は理数系の分野はあまり得意ではありません。そのため素人という立場でなんでも徹底的に質問させていただきます。できる限り録音します。そうした情報を丁寧に整理し、展示に落とし込んでいます。
- 司会
- どちらかというと、社員間の垣根を取り払うというか、「全部知って、さらに深く知る」ということを皆さん心掛けておられると思います。
- 小林
- 特定の部署の扱いが少ないと、社内の協力体制も弱まってしまうことがあります。そのため、すべての部署をできるだけ均等に扱うという姿勢で臨むことが、長期プロジェクトには必要だと考えています。



人を惹きつける生のアテンドの力
- 司会
- これは私の持論ではあるのですが、企業博物館には基本的にアテンドがつかないといけないと考えています。ただ見るだけではなく解説を聴くことで、知見も深まるし、その企業への認識も深まっていく。アテンドの重要性に関してどう思いますか。
- 渡邉
- いつでもそう思います。「JALスカイミュージアム」を訪れた際、OBの方の説明がピカイチだったのです。その話を聴くだけで、それまでANA派だったのですが鞍替えしました。また企業博物館では、語り方、語る口調によってその企業の色が見える。広報誌だけでは理解できないその企業の「人格」が見えてくる。
メディアとして企業博物館を考えると、マスのCMとは異なりますが、来館者も限られるような施設であっても、その人格を知り、企業の愛着まで持っていくには、どこでも見える情報だけじゃなくて、人を介して見ることで、初めて企業の企業体というか、そんなところが見えてくるのだと思います。
- 小林
- あるコンペで丹青社さんに敗れたことがあったのですが、丹青社さんは退職された技術者の方々を施設のアテンダントとして起用するという提案をされたとうかがいました。一方、私たちはそれをデジタルで表現するという提案をしていました。そのため、来館者はデバイスを渡すことで対応できると考えたのですが、クライアントは「生なまの力」の方が強いという判断だったのです。
- 司会
- 私はある薬品関連のミュージアムで体験したのですが、すべてデジタル対応。女性のアシスタントの方がおられるのですが、デジタルの操作がわからないときだけ対応するというスタイルでした。物足りなさを感じました。
- 島村
- 最近はクライアント側がデジタルを主体にしてほしいというスタンスが多くなっているようです。でもこちらの立場としては、来館者がリアルな場に来ているからこそ、アテンダント役がいた方が良いという考え方を勧めます。
- 司会
- コロナ禍の最中に、自動車メーカーの方とオンラインで話をしていたのですが、話の内容に共感しました。彼が言うには、面と向かって話をしていると、その来館者の興味関心に併せて解説を変化させると言われたのです。私は「まほうびん記念館」で5年過ごしたのですが、のべ6000人の方に対応しました。まったくそのやり方なのです。興味関心のある部分を強調することで、来館者の態度変容が起こる。来館者が退出するとき「とても興味深い見学だった」という感想を数多くいただきました。
- 小林
- 案内する担当者の力量がいろいろあるので、デジタルは一旦平準化するためのサポートとしてあっても良いとは考えています。
- 司会
- こうしたことはBtoBもBtoCも同じだと考えて良いですか。
- 小林
- BtoBの方がやっぱり難しいのです。薬品関連もやはりそうでしょうね。BtoBは確かに難しいのですが、わかりやすくしてしまうと、そぎ落とされる情報が多いので、研究者の方のフォローがあったりする施設の方が評価は高いと思います。
パネルや映像だけでは記憶に残りにくい
- 司会
- 事前に2013年に本誌に投稿された「鳥居論考」(注1)をお渡ししましたが、BtoBに関して言うと本当に唯一の論考だと思います。調査の結果でも展示や解説に工夫を加えることで、来館者の評価も高まるし、その後の情報拡散にもつながっていることが証明されています。
- 渡邉
- やはり島村さんが手がけられた、「みなとみらい」の電子部品メーカーの施設は整っていると感じました。技術展示の個所でも、言葉の使い方が非常にうまい。専門家向けの言葉と、そうでない場合の言葉使いをうまく処理している。より深く知りたいという、情報をわけることが必要だと思います。
- 司会
- 「みなとみらい」にある資生堂の「ShiseidoBeauty Park」は、数年前ヒアリングをしたのですが、その時点では、技術者と来館者の対話を念頭においてつくられたと伺いました。そのため同じ資生堂でも静岡県掛川の「資生堂企業資料館」とはまったく異なるアプローチですね。「みなとみらい」の電子部品メーカーのアプローチはいかがですか。
- 島村
- そうですね、アテンダントが必ずつきます。知識レベルが異なる来館者やリピーターの方もいらっしゃるので、興味のありそうな項目は詳しく説明するなど柔軟な対応が必要です。パネルや映像を見るだけで終ってしまうと、記憶に残る割合が薄まってしまい本質の部分が伝わらない恐れがあると思います。
企業博物館にナラティブ(物語)化は大事
- 司会
- 昨年本誌に投稿した論考で「企業博物館とナラティブ」(注2)というものがあるのですが、一般の博物館・美術館はその施設のコンセプトに従った作品を展示しているので、個々の作品の解説はあってもナラティブ(物語)化は難しいが、企業博物館は設置企業の歴史を追うので、必然的にナラティブになってくるのではないかと書きました。このへん、どう考えられますか。
- 渡邉
- ナラティブということは私自身でも大事にしています。どの企業でもそうですが、最初に熱い志があって創業し、ベンチャーとして企業ははじまる。その熱いもののつながりが、画像や事項として年表などで表現されていますが、まさにそれを物語として、どのような視点で語るのかは、企業博物館にとって最も大事なポイントだと思います。
創業の時は創業者の語り口や空気感が大切ですし、現在では多様なステークホルダーへの伝え方など、語り方も時代を通して変えていかなければならないと思います。そのつなぎ方をどのように表現するのかをストーリー化していく。ナラティブの表現は企業博物館として大事だと思います。
- 小林
- いま渡邉さんが言われたことは、私自身の没入感にもつながります。インフラ系の企業に関わっているのですが、その恩恵を受けていない人などいないのです。そのため年代を通したストーリーづくりに自分も関わっていかなければならない。味の素にも関わっていたことがあるのですが「うま味」や「Cook Do」というイメージが強い一方で、パソコンのCPUの絶縁材を作ったり、活性炭をはじめとする吸着剤のような化学的なものも扱っていたりする。すなわちBtoCとBtoBが混在している。BtoC企業として知られている顔を、皆が知らないBtoBの側面ではどのように表現するのか、ナラティブな表現で解決していかなければならないと考えます。
- 島村
- その商品に隠された開発秘話のようなものがヒアリングを重ねると山ほど出て来る。そこをどう伝えるのか、言えること、言えないことを含めて、展示で一番面白いことを物語で伝えたいと考えています。
- 司会
- 京都府綾部市に「グンゼ博物苑」があります。ストッキングのパッケージで開発した製品をほかの用途で利用できないかという課題があったのですが、一人の技術者がカニ漁の漁船に乗り込んだのです。それも二カ月も。カニの足は一本でも欠けると、商品価値が極端に下がってしまうのです。そのパッケージでカニを包むと、折れない。見事に商品化につながったのですが、このような発想、また、トライ。このようなことを説明するには、まさにナラティブでの表現が最適ですね。
- 小林
- このようなことを展示で表現するには、製品の通常の用途ではなく、その背後にある機能としての価値、例えば「柔らかくて破れにくい」という機能に、一旦抽象化して伝えていく必要があります。そのプロセスには人のファシリテーションが入ってくるので、空間や展示ではあくまでもサポートツールなのかなと思います。
- 島村
- 先程からの話では、イノベーションセンターでの展示の必要性が強まってきていると思います。技術者にはたくさん話題やヒントもあるので、コミュニケーションツールとして利用ができますね。
- 渡邉
- 企業の上層部の方々が共創とかイノベーションということをここ数年当たり前のように使い始めるようになってきたのですが、コストパフォーマンスの問題もあってただ一つの施設での表現は難しい。ただ歴史を踏まえて、今までの歴史を語るだけではなく、今の事業にどのように結びついてきたのかまで語ることによって、社員教育にも使えるし、コマーシャルベースにもなるかもしれない。その意味でも企業のDNAを軸足として伝えることは説得力もあり、大切なことですね。


失敗もチャレンジの歴史
- 司会
- 「パナソニックミュージアム」に16回ほど通っています。松下電器時代、不況下で売り上げが上がらない。全国の代理店が集合した会合で、かなり抗議がでた時、松下幸之助が「我々が悪かった」と発言するのです。この映像は以前は検索すると出現したのですが、現在では一般展示で出てきます。なかなかできないことですが、この決断は見事だと思いました。
- 高柳
- 失敗の話とか、それが発端となって引き起こした会社の危機の話、そうした危機を克服し、乗り越えたことをストーリーとして紹介することは、来館者にとっても、社内向けにも有効なことだと研究でも言われています。
- 渡邉
- 航空会社や鉄道会社で、失敗や昔の事故について取り上げることがあります。展示するかどうかで担当の方々と激論になることがあるのですが、失敗をしながら克服できたということは、企業のチャレンジの歴史として取り入れていくことが私には大切だと思います。
- 司会
- 今は閉鎖しましたがLIXILのミュージアムで焼け焦げた便器を展示してあったのを見た時はおどろきました。通電不良が積算され、このような事が起こってしまったと説明を聴かされましたが非常に印象に残っています。「まほうびん記念館」ではバブル期に5万円のポットを売り出したことがあって、それも展示してあります。
- 高柳
- 当時を知らない世代にとって「まほうびん記念館」のバブル期のポットの話は、聴くことによってバブル期を追体験できるという価値もあります。商品開発において、社内でもこんなことが語られていたのがバブル期の特徴だったということが認識できたりもします。
インナー向けの情報発信はもう一つの役割
- 司会
- さて最後に残っているテーマがあります。インターナル・コミュニケーションというテーマです。このことの認識に至ったのは2012年です。武田薬品工業の常務にヒアリングしていて気付きました。武田は数多くのM&Aを実施していますが、M&Aした先の社員教育用に武田史料館を利用しているというのです。この施設は、社内施設であり一般には非公開なので、常務に聴いた部分だけ披露しますが、武田にとって非常に大切な施設なのです。
ここ数年、このように一般公開されない企業資料館の施設が目立ちます。企業の国際化、M&Aなどによって、ルーツの異なる社員、グループ社員が増加している。彼らにその企業の企業理念を植え付けるために企業博物館の機能を利用するというものです。この点について皆さんのご意見を伺いたいと思います。
- 渡邉
- 私がいま担当している企業博物館も、そのケースが当てはまります。企業理念をどう継承していくのか、ひと時代前は、研修施設としてかなりクローズ化された限定的な施設だったのですが、最近では公開され始めたというのか、一般も見ることができるようになっていると思います。典型例として「松下幸之助歴史館」と「稲盛ライブラリー」をあげたいと思います。
それと担当した例で言うと「オリンパスミュージアム」があげられます。この施設は改装の際、メインターゲットは社員にしたミュージアムをつくりたいという依頼でした。求心力というのは企業にとってどうしても必要なもので、理念を伝える場はどうしても必要という事だったのです。その場として企業博物館の存在がある。
- 島村
- 私が担当した電子部品メーカーの施設も、まったく同じ方針です。急激に海外の社員数が増加し、一気に7万人になりました。この会社は創業者がつくった社是を大切にしています。その想いやニュアンスを海外の社員にも、どのように伝えるのかを腐心されていました。施設での研修は、設立以来、幹部社員、中堅社員、新入社員の全社員ですが、製造勤務者には、ラインを止めるわけにはいかないので、WEB会議でつないで見学体験するという方法も行っています。インナー向けに企業の精神をどう伝えていくのかが、企業博物館に与えられた責務になっていると感じます。
- 渡邉
- 私が担当していたキヤノンも、買収などでいろいろなジャンルを増やしていったので必要です。東芝の医療機器部門を買い取ったこともあって、たしかにそのようなニーズは感じます。
- 小林
- 私が担当している日本ガイシも、グローバルに展開している企業です。そのため、海外拠点の社員同士がつながり、コミュニケーションを深められるようなコンテンツを現在計画しています。企業ミュージアムは、これまでは広報部門が主に担うケースが多かったのですが、日本ガイシのプロジェクトでは、人事部門や、新製品の創出・事業化を推進する部門など、さまざまな組織が関わっています。
一つの施設をつくることで部門間に一体感が生まれ、これまで関わりのなかった部門同士がつながり、このプロジェクトを通して社内がつながっていくことを目の当たりにしています。この施設の名称は、挑戦の歴史を背景に、Diversityをもって未来にDiveする、という思いを込めて「NGK Collaboration Square DIVERS」と名付けられました。
ますますエンターテインメント化が進む
- 高柳
- これまでの皆さんのお話を伺って、あらためて強く感じているのは、いわゆる企業博物館や企業ミュージアムの登場と発展というのは、ディスプレイ業の方々が起こしたイノベーションだということです。ディスプレイ業の方々は、企業博物館や企業ミュージアムが登場する以前から、博物館の展示づくりに関わってきたほか、博覧会や見本市、商業施設のディスプレイなどの担当実績を蓄積されてきたと思います。それらが結晶するようなかたちでできたのが企業博物館や企業ミュージアムであると感じています。また、現代までの発展についても、ディスプレイ業の方々がさまざまな事業で得られた経験やノウハウを反映させるような形で実現されてきたと言えるのではないでしょうか。
それらを踏まえて、これからのBtoB企業の企業ミュージアムの発展について予想をお聞きしてもよろしいでしょうか。
- 渡邉
- わたしはもっとエンターテインメントの要素が増えていくと考えています。ここしばらくの傾向ですがBtoB企業がCMを投下するようになってきました。いろいろな手法を駆使することで知名度があがると、やはり効果的なのだという認識が生まれてきたのではないでしょうか。それが高じてエンターテインメントに志向していくと考えられます。エンターテインメントだからこそ、生活者へ自社の所有している技術やサービスの評価を認識してもらえる機会が高まることにつながると思うのです。そういったものに展開していくのではないかと考えます。ディズニーランドの例で言うと、presented byなのか、supported byなのかということです。インターナル・コミュニケーションの中に入っていたものが外の立場から見ると、新しい情報や新しい発展につながる。それが興味関心を引く、知的好奇心を向上させていく。企業としての健全性を披露する場でもある訳です、企業博物館は。
- 小林
- これまで企業として公にしづらかった情報も、「意外とオープンにしても良いのでは」という風潮が徐々に生まれてきているように感じます。情報公開のハードルが下がることで企業が保有する情報そのものも、今後ますますオープンになっていくのではないでしょうか。
そうした流れの中で、業界全体を横断・統合するかたちで、複数の企業が共同で運営する「業界の博物館」のような施設も生まれてくると思います。
- 司会
- 今日集まっていただいた、プランナーの方々による座談会は、これまでは開催されたことはなかったと思います。その意味でも、初めての試みでもあり、また内容も充実し非常に意義のあるものとなりました。ご参加いただいた皆さまに心から感謝致します。ありがとうございました。

注1 「鳥居論考」鳥居敬
2013 年『BtoB コミュニケーション』誌3月号に掲載された論考。「BtoB製造業のコーポレート・コミュニケーションにおける企業博物館の有効性」がタイトル。自身で手がけたカワサキワールド(川崎重工業の企業博物館)を通して、BtoB企業の企業博物館がどのような役割を果たすのか、アンケート調査を踏まえて、その実証性を明らかにしたもの。
注2 「企業博物館とナラティブ」粟津重光
2024年『BtoBコーポレート・コミュニケーション』誌3月号に掲載された。筆者の経験から、企業博物館では館内の解説はナラティブ(物語)で語られている。また、その方法が企業博物館にとって有効な手段であると主張した論考。